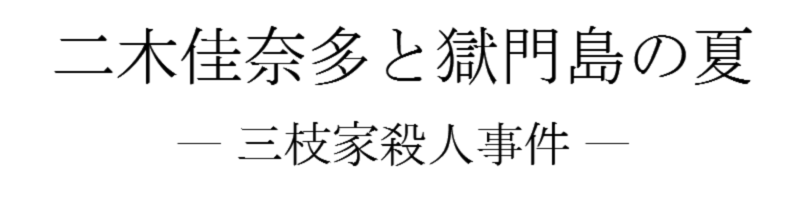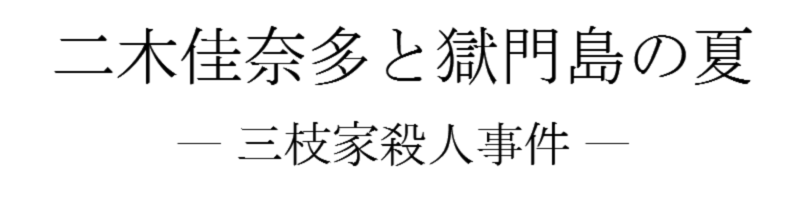甲板から眺める夏の海は、茫洋と広がり、気の遠くなるような暑さを空間的に体現しているようだった。
ただ、影ひとつなく、ひたすらに射す日差しの中、吹く風だけが僅かばかりの爽やかさを含んでいた。
その向かう先に、大きな島影があった。伊豆元島だ。
船は、清水港を出て、伊豆半島の土肥、松崎の各港を経て、伊豆元島に向かっていた。
合計4時間ばかりの船旅だった。
伊豆元島には、東京からでも、僕たちが乗っている型の客船で10時間、高速船であれば3時間で着くことが出来る。
さらに、島には空港もあって、小さな定期便が通っているから、羽田空港から数十分だ。
近代以前ならともかく、今では、離島と云うには、些か便がよすぎる。
首都圏近郊の手近な観光地、といった立ち位置が、正直なところだろう。
だが、安穏とした旅行、という気分にはどうしてもなれなかった。
当然と言えば当然だった。僕たちの旅行の目的地は、風光明媚なる観光地、伊豆元島ではない。その先に浮かぶ小さな島、北門島なのだ。
北門島――三枝家の島。
二木さんと葉留佳さんの実家であり、2人を苦しめてきたその原因であるところの、三枝家のある島。
「そろそろ、見えてくるはずよ」
僕の横で海を眺めていた二木さんが、ぽつりと言った。
その視線の先を追う。そこには相変わらずに、伊豆元島が泰然と浮かんでいた。
そして、その島の影から、またひとつ別の島影が現れた。伊豆元島のそれよりも、少しだけ、色が褪せている――。
「あれが……北門島?」
「そう。獄門島」
目を細めて島を見つめたまま、振り返りもせず、二木さんは僕の問いかけに短く答えた。
北門島――通称、獄門島。
その話は幾度となく聞いていたけれど、その姿をこの目で見るのは初めてだった。
鬱蒼と茂る森が、島を覆い尽くしている。
深すぎて、むしろ黒に近い緑が、島の色だった。
浜近くに見える小さな集落は――それでも島の中心部なのだろう――夏冬の風雨に耐え、色褪せた、如何にも年季の入った建物が並んでいる。
港には、この島のささやかなる産業を支えているであろう小さな漁船が並んでいる。
まるで、時代に取り残されたような、鄙びた島だ。
あの島に、三枝家があるのだ――。
ぞくり、と背筋が震えた。
どおおん……。
ずっしりと響くような音が、遠くから聞こえてた。
遠雷だった。
空気の温度が、すっと下がった。
島の向こう、水平線の辺りに、積乱雲が湧き出して、ゆっくりと、しかし確実に大きくなっていく。
白く美しく映えるその姿とは裏腹に――嵐が近づいていた。