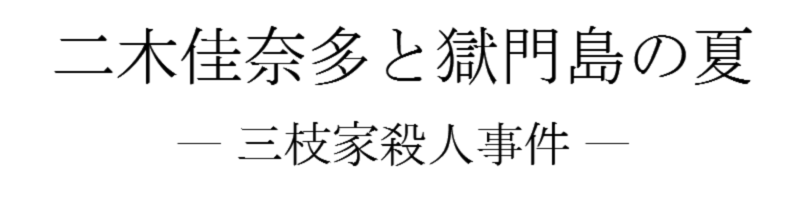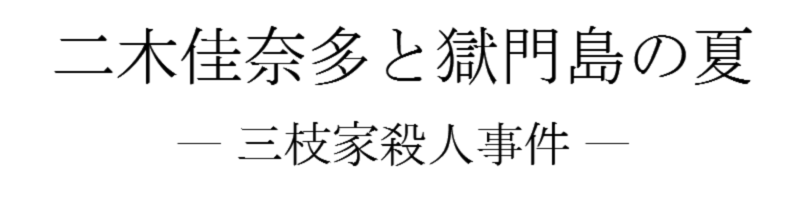「う…ん…」
差し込む日の光と、微かな異音で目が覚めた。
枕もとの携帯を見る。
「…えっと…」
時間は…、7時半!
「寝坊したっ」
慌てて飛び起きた。
改めて携帯をチェック。
二木さんからのメールがきていた。
『おはよう、理樹』
『おはよう?』
『おはよう。』
『』
うわああーっ。
最後のとか、空メールだよ……。
「ごめん、今起きたよ…」
送信。
すぐ電話が掛かってきた。
「おはよう二木さん」
『おはよう。随分とゆっくり寝てたみたいね』
「ごめん…」
『ま、休みだし、仕方ないけどね……』
電話の向こうの二木さんは呆れているようだ。
『寮の外で待ってるわよ』
「うん。待ってて二木さん」
ぴ。携帯をたたみ、僕は急いで身支度を整えにかかった。
「二木さん、ごめん。お待たせ」
「おはよう、直枝」
「二木さんは、朝も早いね」
「仕事が溜まってるから。自分の時間は朝方に作らないと」
「そういえばこの夏は、寮会の仕事ばっかりやってる気がするよ」
「仕事に追われるからこそ、自分の時間は意識して作るものよ。意識してみると良いわね」
「うん……そうだね」
「さ、仕事の前に食堂に行きましょ。ちゃんと朝ご飯を食べないと頭が動かないわよ」
「そうだね……行こうか」
「今日はどうしようかしら……」
といっても選択肢はA定食かB定食しかない。
「今日のB定食はなにかな」
「ミックスサンドとミックスサラダね」
洋風朝食セットといったところか。
「Bにしよう。二木さんはどうする?」
「直枝と同じにするわ」
「そっか」
ぴ。ぴ。食券を買う。
「トレイは僕が運ぶから、お茶用意してくれないかな、二木さん」
「そうするわ。あ、直枝」
「うん?」
「座る席、窓際のテレビが見られる席にしてもらえる?」
「うん、いいよ」
「じゃそこにお茶持っていくから」
二木さんが給湯機へ向かう。
カウンターでB定食セットをふたつ、受け取って窓際の席へ。
二木さんは窓際の席でテレビのリモコンを持って座っていた。
緑茶の香りがふわりと漂っている。
どうしてかと思ったら湯飲み茶碗が4つも用意されていた。
『それでは、次は伊豆元島からの中継です……』
「……」
「二木さん、お待たせ」
二木さんは窓際の席から見えるテレビに向けている視線を戻した。
修学旅行後ぐらいだっただろうか。
アナログテレビが液晶テレビに代えられたのは。
「おかえり、直枝」
トレイをおいて椅子に腰掛ける。
「ローカルニュース?」
「そうよ」
「ふうん……平和だね、なんとも」
「そうでもないわよ、ほら」
『……静岡地検特捜部は、今回の贈収賄事件と脱税事件について……』
「あ、これ……」
「そ。ろくでもない話ね」
「…僕らの知らないところでは、まだ色々なことが続いてるんだね」
「そうね。でも、あとは警察と司法の手に任せるだけよ」
二木さんは、そこで少し言葉を止めた。
「……感謝してる。本当に」
「僕だけの力じゃないよ。来ヶ谷さんに、鈴に……みんなの力だよ」
「全部ひとりでだなんて、そんなことができるのは奇跡を起こせる本物の神さまだけよ」
「私たちは神さまでじゃないんだから、奇跡なんて起こせない」
つけあわせのクレソンをよけてから二木さんはサンドイッチをつまむ。
「だから私たちは、私たちみんなで進んでいくのよ」
「陳腐な表現だけど、力を合わせて……ね」
二木さんも、随分と丸くなったものだと思う。
もしかしたら、本来の二木さんに戻りつつあるのかも知れない。
それはきっと、いいことなのだろう。
「直枝」
サンドイッチを淡々と食べていた二木さんは僕を呼んだ。
「どうしたの、二木さん?」
「このミックスサンドのうち、どれが苦手?」
えっと。ミックスサンドをしげしげと見つめた。
卵サンドがふたつ、サラダサンドがふたつ、ハムカツサンドがふたつ。
「卵サンドかな?」
強いて言えばだけど。
「じゃ、私のサラダサンドをあげるから、卵サンドを頂戴」
「うん、いいけど。どうして?」
「トマトが入ってるのよ、これ」
二木さんは、手のつけられていないサラダサンドを掲げてみせた。
確かに断面からは赤がのぞいている。
トマトの赤だろうか。
「ほんとだね。じゃふたつもらうよ、二木さん」
二木さんの皿には、卵サンドが4つ並んでいる。
ちょっと朝からどうかなと思わなくもないけど。
「……」
二木さんが喜んでいるのなら、問題なし、かも。
『…以上、伊豆元島からお伝えしました。次のニュースです』
テレビからトレイの上に視線を移す。
サラダサンドには、和風ピクルスがたっぷりと入っていた。
これはこれで、結構美味しい。
「この和風ピクルス、誰が漬けてるのかなぁ。食堂のおばちゃんかな」
「私よ」
「わぁっ」
「びっくりした。なんだ寮長ですか。おはようございます」
「はい、おはよう。かなちゃんもおはよう」
「おはようございます」
「それから、かなちゃんって呼ばないで下さい」
「佳奈多さん、リキ、ぐっどもーにんぐ、なのです」
少し幼い声に顔を上げる。
マントを羽織った女子生徒――クドが立っていた。
いつもの笑顔のまま、彼女は二木さんの向かいに座る。
「おはようクドリャフカ。……あーちゃん先輩、お茶淹れてありますから、どうぞ。クドリャフカもね」
「わふーっ、べりーさんくすですっ」
「ありがとう、かなちゃん。用意がいいわね」
「ふたりが来る時間くらい、大体判ります」
「ぬるめが好きだったと思いましたが」
「それと、かなちゃんって呼ばないで下さい」
「何かこだわりでもあるんですか、寮長?」
「食後は熱いのがいいんだけど、朝起きて飲むのはぬるめがいいわねー」
そんな会話をしている間もクドはせっせと箸を運んでいる。
部長とクドはA定食のようだ。
鮭の塩焼きに昆布巻きにみそしるたまごやき、とオーソドックスな和定食。
「そういえば、食堂の給湯器の温度なんですけど」
「調子おかしい?」
「少し温度が高い気がしました。湯飲み茶碗持つとき、ちょっとこう、ぴりってきた感じです」
「あれもおんぼろさんだからね」
「あとで機械を見てもいいですか?」
「いいんじゃない? なおせる?」
「なおせるかどうかはわかりませんが、悪いところはわかるかもしれません」
「お願いね、クドリャフカ。できれば、お茶はおいしいのを淹れたいわ」
「はい、うまく直るといいのですけど」
「給湯器の管理も家庭科部の仕事なの?」
「時々頼まれて調子を見ているのですよ」
「機械いじりは嫌いではないですから」
「そういえば、給湯器の脇に貼ってある『美味しいお茶のいれかた』っていうポスターは私が書いたのです」
「え? そうだったの? すごい達筆だったから先生の誰かかと思ってた」
「能美さんは習字やってたんだっけ」
「いちおう初段免状を持っているのですー」
「私のお師匠さまはおじい様なので、お仕事忙しくなってからそこで止まってますけど」
「クドリャフカ、うちの主将がお礼言っといてって。ありがとうって」
「私の字なんかでよかったんですか?」
「何か書いたの、クド?」
「応援の字幕とお祝いの字幕を書いたんです」
「『地区大会優勝おめでとう』と『ブロック大会優勝おめでとう』と『全国大会優勝おめでとう』というやつです」
「優勝する気満々なんだ……まぁうちの剣道部はこの辺りじゃ強い方らしいから、わからなくはないけど」
「ある種のプレッシャー療法ですよねー」
「主将もほんとおめでたいわ。大会の結果なんてどうなるかもわからないのに」
「あと『夢をありがとう』というのも書きました」
「…………」
「そ、そういえば謙吾から聞いたけど、夏休み中の剣道部は相当ハードな合宿らしいね」
「例年通り山に行っているだけよ」
「山ごもりですか。それはべりーはーどです」
「きっと滝に打たれたり、タイヤを背負って崖を登ったり、熊と戦ったりしてるのですね!」
「剣の道は和の心です!」
「クドリャフカ、腕を振り回さないで」
「わふ、ごめんなさい」
「二木さんは合宿、参加しないんだね」
「そりゃーかなちゃんは幽霊部員ですもの」
「かなちゃんって呼ばないで下さい」
「私は寮会の仕事を優先しているだけです」
「ふうん? 寮長さん『たち』も大変だわね?」
「からかわないで下さい。本当に、結構な量なんですから、仕事」
「そういうことにしておきましょうねー」
部長にあしらわれている姿を見てクドはくすくす笑っている。
「やれやれなのです」
僕も苦笑した。
「ごちそうさまでした」
ぱん、と手を合わせるクド。
「ごちそうさまでした」
二木さんは、小さく手を合わせて言った。
「ごちそうさまでした」
僕も、一緒に手を合わせて一礼。
夏休みになって、クドとごはんを食べる機会が増えるにつけ、二木さんも僕も、同じようにするクセがついた。
食べ終わったら大きな声でごちそうさま、って言うのはちょっと恥ずかしいけど。
クドは本気で食べ物の神さまに祈りを捧げているような真剣さなのでつられてしまうのだ。
「さて、と。それじゃかなちゃん、直枝くん、行きましょうか」
「かなちゃんって呼ばないで下さい」
「なにか用事ですか?」
「寮長の仕事の引き継ぎよ。もうほとんど覚えているのに」
「そう言わないの。ほら、ちゃーんと引き継ぎをしていますって形を見せておくと上がるかもしれないでしょ」
「なにがあがるのですか?」
「私の内申書とか」
「ああ…」
「わふっ」
「そんなことの為に連れ回される私達の身にもなってください」
「ふふっ、あなたたちも三年になればわかるわ」
「内申書なんて普段の行いの結果です。素行を正していれば取り繕う必要もありません」
「出来る人に出来ない人の気持ちはわからないものよ」
部長、自分で自分を出来ない人と言っていることに気付いているのかな…。
「さ、行くわよ。寮の中にはまだあなたたちが知らない未開の扉が存在するんだから」
「はいはい、わかりました、わかりましたから引っ張らないで下さいっ」
困った上司に無理矢理付き合わされる部下ってこんな感じなのかもしれない。
「佳奈多さん、リキ。ふぁいと、なのですー」
クドの声に見送られながら、僕たちは食堂を後にした。